はじめに
「5Sが大事なのは、わかっている。
だけど、現場ではなかなか続かない──」
そんな声を、これまでに何度も耳にしてきました。
整理・整頓・清掃・清潔・しつけ。
この5つの言葉は、どんな職場でも一度は聞いたことがあるはずです。
でも実際には、
- 「始めたけど、気づいたら元通り」
- 「結局、誰もルールを守っていない」
- 「やらされ感があって、続かない」
そんな現場のリアルと向き合っている方も、多いのではないでしょうか。
じつは、私自身もその一人でした。
食品工場で品質管理の仕事にたずさわるなかで、
社内で5Sプロジェクトを立ち上げたこともあれば、
外部コンサルの指導のもと、半ば強制的に進めた経験もあります。
今でも、毎朝「5S唱和」を続けている現場にいます。
それでも──浸透させるのは、簡単なことではありませんでした。
この記事では、「5Sが続かない理由」について、
やさしい物語とともに、少しだけ深く考えてみたいと思います☘️
舞台は、仮想のカフェ「アイボリー」。
日々のちいさな出来事のなかに、現場での気づきやヒントが隠れています。
どうぞ、お好きなドリンクを片手に、
ゆったりした気持ちで読み進めてみてくださいね。
本日の物語
では、ここからは──
「カフェ・アイボリー」で紡がれた、やさしい一杯の物語をお届けします。
☘️ ごゆっくりお楽しみください。
📘 第1話:「安心って、なんだろう?」
「HACCPってむずかしそう…」
そんな声に、何度も出会ってきました。
このnoteでは、食品業界で品質管理や品質保証の仕事に長くたずさわってきたコーヒーさん(わたし)が、
カフェや飲食店で働くみなさんに寄り添いながら、
“安心を育てる”やさしい衛生管理のヒントをお届けしています☘️
舞台は、仮想のカフェ「アイボリー」。
スタッフとの会話や日々の出来事を通して、
HACCPや衛生管理の“ちいさな気づき”を、物語と一緒に紡いでいきます。
🕊 この投稿を読み終えたとき──
「片づけることって、
安心を育てるやさしい習慣なんだな」
そんな静かな気づきが、
ふっと心に灯りますように☘️
はじめて知った「5S」の不安
──アイボリーの午後。
いつものように閉店準備を進めながら、かんなちゃんがふと話し始めた。
「ねぇ、コーヒーさん、なーみんさん。
この前、ネットの記事でね、“5Sが衛生管理の基本”って紹介されてたんです。」
「うんうん、5Sね。よく聞くけど…読んでて何か引っかかった?」
と、なーみんがやさしく問いかける。
「そうなんです。
私、この前までHACCPとか表示とか色々学んできて、ちょっと自信がついてたんですよね。
“私、だいぶ分かってきたぞ!”って。
でも、5Sの説明を読んでて……」
かんなちゃんは、少し照れくさそうに笑った。
「“あれ? 5Sって、ちゃんと説明できるかな?”って不安になって…」
「うんうん、それは良い気づきだね」
コーヒーさんが微笑む。
「それでね、昨日お母さんと一緒に記事を読んでたら…」
かんなちゃんが少しだけ顔を赤らめる。
「お母さんが、“5Sって何?”って聞いてきて──
私、焦っちゃって、“整理・整頓・清掃・清潔・しつけ、要はキレイにすること!”って、
すごく曖昧に答えちゃったんです…。」
「なるほど〜」
と、なーみん。
「頭では“5Sは大事”って分かってても、いざ誰かに説明するとなると、意外と難しかったりするよね」
「そうなんです…
それで今日、もう一度ちゃんと整理したくて、教えてほしかったんです!」
「整理」──いらないものを手放す力
「じゃあ、せっかくだから今のタイミングで一緒に振り返ろう☘️」
と、コーヒーさんが軽く手を叩いた。
「まずは【整理】から。
これは──“必要なもの”と“いらないもの”を分けること。」
「たとえば…?」
「使わない備品が山積みになってたり、“いつか使うかも”で取っておいた容器や資材が残ってたり。
そういうモノが多いと、汚れや異物に気づきにくくなるし、古い在庫の期限切れにも気づきにくくなるんだよね」
「確かに…うちも時々、奥の棚に“忘れてた備品”ありますもんね」
「そう。整理って、単にキレイに見せるだけじゃなくて、
“リスクを早く見つけるための整理”なんだよ☘️」
「整頓」──誰でも迷わない仕組みづくり
「次は【整頓】!」
と、なーみんがバトンを引き取った。
「これは“使うものを使いやすく並べる”工夫だよ」
「使いやすく?」
「うん。たとえば──
・どこに何があるか、誰が見てもすぐ分かる場所に置く
・置き場所にラベルや名前を書いておく
・使う順番に並べる──なんていうのもすごく効果的だよ」
「そうか…“探し物”を減らせるんですね!」
「そうそう。探す時間って、毎日少しずつ積み重なると意外と負担になるし、
迷うことで間違いのリスクも高まるからね☘️」
「清掃」──気づきの力が、未来を守る
「そして、【清掃】。」
コーヒーさんが再びやさしく話し出す。
「“清掃”って言うと、“掃除”って思いがちだけど──
実は“点検”の役割もとても大きいんだよ。」
「点検…?」
「うん。掃除をしながら──
・異物の混入跡がないか?
・機械が変な音してない?
・水漏れしてないかな?…って、小さな異常にも気づける。
毎日の“ちょっとした気づき”が、
未来の安心につながっていくんだよ☘️」
「なるほど…掃除しながら点検するって、すごく納得です!」
キレイは「安心のため」に
「……こうして整理・整頓・清掃を日々積み重ねていくと、
“キレイだから安心”じゃなくて、
“安心のためにキレイにする”っていう意識が育っていくんだよね」
と、なーみんがやさしくまとめた。
かんなちゃんは、うんうんと何度もうなずきながら──
「今日もまた、新しい安心の芽が育った気がします☘️」
──そんなやさしい空気が、今日もアイボリーに静かに流れていた。
🍀 読後のひとことメモ
「整理・整頓・清掃」は、
難しいことじゃなくて、
“小さな気づき”を育てる一歩。
今日の整理が、明日の安心を支えています☘️
──いかがでしたか?
小さな会話の中に、安心の“はじまり”がそっと描かれていた第1話。
続いては、清潔を育てていく“土台づくり”に目を向けた第2話です☘️
📗 第2話:「清潔を育てる、ということ」
🕊 この投稿を読み終えたとき──
「“清潔”って、“汚れを取ること”じゃないんだ」
そんな新しい視点が、静かに芽生えますように☘️
清掃と清潔は違う
──アイボリーの午後。
閉店準備をしながら、かんなちゃんがまた声を上げた。
「コーヒーさん、なーみんさん。あの…前回5Sの話、すごく勉強になったんですけど──」
「うんうん、どうしたの?」
と、なーみんがにこやかに振り返る。
「実は…その後ネットでまた記事を読んでたら『清掃と清潔は違う』って書いてあって。
あれ? どう違うんだろうって、ちょっとモヤモヤしちゃって……」
「いい視点だねぇ」
と、コーヒーさんも頷く。
「じゃあ今日はその続きを、もう少し深掘りしてみよう☘️」
🧽 清掃とは「汚れを取ること」
「まず【清掃】は、言葉通り“汚れを取ること”だよね」
と、コーヒーさんが説明を始める。
「たとえば、調理台を拭いたり、床を掃いたり、道具を洗ったり…毎日の“お掃除”のこと」
「うん、それなら私も分かります!」
「でも【清潔】は、その先にあるんだよ」
と、なーみんが優しく続ける。
「清潔っていうのは、“汚れにくい環境を作ること”なの」
「汚れにくい環境…?」
「たとえば──
・物の配置を工夫して掃除しやすくする
・排水溝や排気の湿気を溜めにくくする
・通気を良くしてカビが生えにくい空気の流れにする
・洗浄の頻度をあらかじめ決めておく──」
「なるほど… 汚れる前に工夫するってことなんですね」
「そう! “汚れてから対応する”より、“そもそも汚れにくい現場を育てておく”ことが清潔なんだよ☘️」
👨🍳 ペリーさんの「整え時間」
──そこへ、ちょうど厨房からペリーさんが顔を出す。
「みんな、楽しそうに話してるネ〜☕️
あ、今日のカウンター周りも整理バッチリだよ〜!」
「ありがとうございます!ペリーさんの“仕込み前の整え時間”も、まさに整理整頓のお手本ですよね」
と、コーヒーさんが微笑む。
「そうなんデス!コーヒーはね、クリーンな気持ちで淹れた方が美味しくなるネ〜☘️」
ペリーさんはそう言って、また厨房に戻っていった。
──その一言が、かんなちゃんの胸にもふわりと残った。
「……たしかに。キレイって“安心”だけじゃなくて、“気持ちの余裕”にもつながってるのかも」
🔍 清掃点検の力
「じゃあ…清掃は、清潔の土台みたいなもの?」
「まさにその通り!」
コーヒーさんがうなずく。
「毎日掃除してると、普段は気づかない小さな異変にも早く気づけるからね」
「たとえば──」
と、なーみんが指を折る。
・いつもと違う水漏れに気づいたり
・機械の音がちょっと変だったり
・排水の臭いに気づいたり
「掃除しながら点検もしてるんですね」
「そう。これが清掃点検の力なんだよ。
でも、最終的に目指すのは“汚れにくい現場”を作ること。
それが清潔づくりの第一歩になるの☘️」
🔁 清掃と清潔、どちらも大切
「うーん…なるほど。
清掃も清潔も、どっちも大事だけど──
“清潔”って仕組みなんですね!」
「そうなんだよ、かんなちゃん」
と、コーヒーさんが微笑んだ。
「整理・整頓・清掃で“整った現場”が土台になって、
自然と清潔も保ちやすくなっていく。
5Sはぜんぶつながってるんだ☘️」
──アイボリーに、今日もまたひとつ
新しい“やさしい安心”が芽生えた時間が流れていた。
🍀 読後のひとことメモ
「清潔」は、“掃除の延長”じゃなくて、
“汚れにくく整える仕組み”のこと。
毎日のちょっとした工夫が、
菌やカビの「住みにくい現場」を育てます☘️
──衛生的な空間づくりは、目に見えない努力の積み重ね。
でも、そこには “あたたかい想い”が込められていることに気づかされます。
続いての第3話では、5Sの最後の“S”──「しつけ」の本当の意味を、
やさしく紐解いていきます。
📙 第3話:「“しつけ”って、なんだろう?」
🕊 この投稿を読み終えたとき──
「“しつけ”って、“ルールを守らせること”だけじゃないんだな」
そんな静かな気づきが、そっと芽生えますように☘️
🧭「しつけ」って、どういう意味?
──アイボリーの午後。
閉店後のカウンターで、かんなちゃんがまた声を上げた。
「コーヒーさん、なーみんさん!あの…この前の続き、また教えてほしくて…!」
「うんうん、もちろん。今度は“しつけ”の話かな?」
と、なーみんがにっこり笑う。
「そうなんです。“整理・整頓・清掃・清潔”までは何となくイメージできたんですけど…
最後の“しつけ”って、子どものしつけ…?それとも?」
「いい気づきだねぇ」
コーヒーさんがやさしく頷く。
「5Sでいう“しつけ”は、厳しく注意することじゃなくて──
“良い習慣をチームで育てていくこと”なんだよ☘️」
「習慣…?」
「そう。たとえば──」
と、なーみんが続けた。
「『みんなやってるよね?』って曖昧にせず、ルールはちゃんと言葉にして文書に残す。
誰が見ても分かる形にして、新しく入った人にも同じように説明できるようにする。
そうやって“共有できる仕組み”を作っていくのが、しつけのはじまりなんだよ」
「なるほど…たしかに新人さんに教えるときに、説明がブレると迷わせちゃいますもんね」
「そうそう☘️」
👨🍳 ペリーさん流・仕込みの習慣
そこへペリーさんも厨房からひょこっと顔を出す。
「新人さんに教えるときはネ〜、
『これはココに置くネ』『それはアッチに置くヨ〜』って、
置き場所が決まってると迷わないネ☕️」
「まさにペリーさんの普段の仕込み前準備が、それですよね」
と、コーヒーさんが微笑む。
「決められた置き場所が守られてると、“教えるのがラク”になる。
教えやすい職場は、どんどん育ちやすいんだよね」
「たしかに……私も新人の頃、迷うと焦ってミスしそうでした」
かんなちゃんは、当時を思い出しながら、うなずいた。
「それにね、かんなちゃん」
と、なーみんが少し身を乗り出す。
🌿 5Sのつながり
「新人の視点って、実は改善のヒントにもなるんだよ。
『なんでここにこれがあるんですか?』『こっちの方が動きやすいかも』って声が出てくることもある。
みんなが気づかなくなってた課題が見つかることもあるからね」
「うわぁ…なるほど!」
「“迷わせない現場”は、自然とミスも減るし、教えやすくなる。
こうして良い循環が生まれていくんだよ☘️」
「じゃあ、“しつけ”って、決して怒ることじゃなくて──」
「うん。みんなで守り続けて、文化に育てていくこと」
コーヒーさんがやさしくまとめた。
「もともと5Sは、整理・整頓・清掃の3Sがしっかり整うことで、
ようやく“清潔”が育っていく。
でも、その清潔をずっと保ち続けるためには、
毎日の行動が自然と続く“習慣=しつけ”が必要なんだよ☘️」
「なるほど…5Sって、全部がつながってるんですね!」
「そうだね。整理・整頓・清掃・清潔・しつけ。
この積み重ねが、自然と“選ばれるお店づくり”にもつながっていくんだよ☘️」
「選ばれるお店……」
かんなちゃんの目が、少しキラリと光った。
「たしかに──
安心できるお店って、お客さんも自然と感じ取ってくれてますもんね」
──アイボリーに、今日もまた
小さなやさしい安心が、そっと芽吹いた。
🍀 読後のひとことメモ
「しつけ」は、“注意すること”じゃなくて、
“みんなで育てる仕組みづくり”。
整理・整頓・清掃の積み重ねが、
清潔を生み、
その清潔を守るのが、習慣(しつけ)。
毎日のちょっとした工夫が、
安心を育てていきます☘️
📚 本日の物語を読み終えて
ここまで読んでいただき、本当にありがとうございました☘️
「やさしい5S」のお話も、今回でひとまずおしまいです。
整理・整頓・清掃・清潔、そしてしつけ──
どれも“特別なこと”ではなくて、
日々の中にそっと溶け込む「安心の土台」なんだと、改めて感じています。
アイボリーのスタッフたちの会話が、
みなさんの現場にも、ちいさな気づきの種を届けられていたらうれしいです☘️
👉 目次に戻る
✅ 解説・振り返り|物語の中にあった“視点のちがい”
「清掃」と「清潔」は、違う。
「しつけ」は、怒ることじゃない。
今回の物語では、そんな“当たり前のようで伝わりにくい”視点のちがいを、
やさしい会話の中からそっと浮かび上がらせてくれました。
たとえば──
清掃は、汚れを落とす「日々の行動」。
清潔は、汚れにくく整える「仕組みや環境づくり」。
しつけは、叱ることでも押しつけることでもなく、
「良い習慣を共有し、みんなで育てていくこと」。
それらが自然と積み重なっていくことで、
“安心できる現場”や“信頼されるお店”が、少しずつ育っていく。
物語の中では、そんなヒントがたくさん散りばめられていました。
でも──
「分かってはいるけど、現実はそんなにうまくいかないよ」
そう感じた方も、きっといるかもしれません。
「上の人が動かないと変わらない」
「忙しくて続ける余裕がない」
「一人だけ頑張っても、どうにもならない」
そんな気持ちも、よくわかります。
だからこそ、このあとのパートでは、
「なぜ5Sは続かないのか」
そして
「どうすれば、やさしく根づくのか」
現場の視点から、少しだけ深く考えてみたいと思います☘️
なぜ5Sは続かないのか?
私もこれまで、さまざまな現場で
数えきれないほどの「5S活動」を経験してきました。
- 社内プロジェクトとして掲げられた5S
- 外部コンサルの指導で“評価対象”になった5S
- 毎朝の朝礼で唱和するだけの5S
……でも、それでも、なかなか根づかないのが現実です。
では、なぜ5Sは定着しにくいのか?
その理由は、とてもシンプルです。
「利益に直結しない」
「やっても、すぐに元に戻る」
そんな“がっかり体験”が、いつの間にか
5Sを「やらされごと」に変えてしまうからです。
でも、私は思います。
本当に5Sが根づいた現場は──
生産性も、安全性も、安心感も最大化される。
それは数字では測りにくいけれど、
たしかに“信頼の土台”をつくってくれるものです。
5Sは、“未来への投資”。
評価されなくても、やる価値がある。
そんな信念が、トップや現場から静かに広がっていくとき、
やがて「文化」として根づいていくのだと信じています。
あなたの現場に、やさしい5Sはありますか?
5Sは、トップの習慣。
そして、部下はその背中を見ています。
でももし、今の職場で
「上が動かない」「理解してもらえない」──
そう感じている方がいたら。
どうか焦らず、自分の中から“ちいさな5S”を始めてみてください。
たとえば:
- 「なんとなく使いにくい場所」を見直してみる
- 「掃除しにくい」と感じる場所を、ひとつだけ整えてみる
- 「当たり前」になっているルールを、あえて“見える化”してみる
それだけでも、空気が変わる瞬間があります。
誰かがやってくれるのを待つより、
「自分が安心できる場所」を、自分で育てていく。
そんな姿勢が、やがて周りの誰かに届いていく。
🍀 あなたの現場では、どんな5Sが芽生え始めていますか?
ルールやマニュアルの前にある、
働く人の想いと安心感。
それを大切にしながら、
少しずつ“伝わる衛生管理”を育てていけたら──
そんな願いを込めて、これからも更新していきます。
5Sの物語はひと区切りとなりますが、
また別の角度から「安心を育てるヒント」を綴っていく予定です☘️
あなたの声を、ぜひ聞かせてください☘️
このブログでは、わたし自身のリアルな挑戦や、
食品業界での経験を活かした情報を、
“やさしく・わかりやすく”整理してお届けしていきます。
感想・ご意見・応援のメッセージなど、どんなことでも大歓迎です。
「ちょっと話してみたいな」と思った方は、
コメント欄やInstagramのDMなどで、ぜひ気軽に声をかけてくださいね☕️
また、noteでは、わたし自身の“未来予想図”として描いている
物語シリーズ「カフェ・アイボリー」を連載中です。
これは、品質管理やHACCPの経験を活かして独立した「コーヒーさん」が、
街のカフェや飲食店にやさしく寄り添いながら、
そのお店らしい衛生管理を一緒に育てていく──そんな物語です。
ストーリー仕立てで、やわらかく・ほっとできる雰囲気で、
衛生のことを“気軽に学べる場”として発信しています。
ご興味のある方は、ぜひのぞいてみてくださいね🌿
あなたの中の“ちいさな芽”が、
やさしく育っていきますように──。
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました☘️
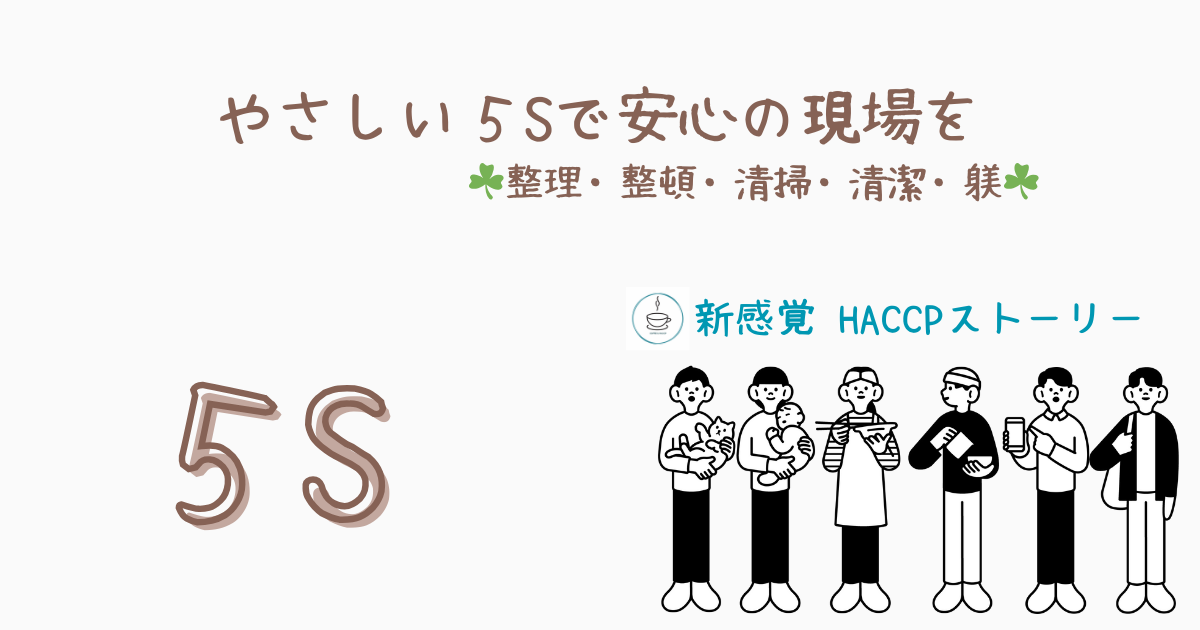
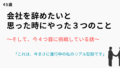
コメント